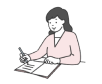介護業界の人手不足、今できる解決策は?外国人採用に注目

介護業界の人手不足、今できる解決策は?外国人採用に注目

介護業界は深刻な人手不足に直面し、多くの施設が運営の危機を迎えています。
今できる具体的な解決策として注目されているのが外国人採用です。
制度の特徴や成功事例を交え、効果的な導入方法をわかりやすく解説します。
本記事のポイント
- 今後の介護人材の不足は?
- 外国人職員を採用するメリットとデメリット
- 人材獲得に成功した事例と共通点
日本全体で深刻化する介護人材不足の実態

超高齢社会を迎えた日本では、介護人材の不足が年々深刻さを増しています。
現場では「人が足りない」が日常となり、施設運営にも影響が及んでいます。
介護職員の需要と供給ギャップは今後さらに拡大する
今後ますます介護職員の不足は深刻化し、2040年には約69万人が不足すると予測されています。
人手不足はもはや一部地域や施設の問題ではなく、全国的な構造問題です。
厚生労働省「第8期介護保険事業計画に基づく介護人材の必要数(令和3年推計)」によると、以下のように介護人材の需要は急増しています。
| 年度 | 必要介護職員数 | 増加数(対2019年) |
|---|---|---|
| 2019年 | 約211万人 | ― |
| 2023年 | 約233万人 | +22万人 |
| 2040年 | 約280万人 | +69万人 |
参照:厚生労働省「第8期介護保険事業計画に基づく介護人材の必要数」
一方、現場ではすでに人材の確保が困難で、特に地方や中小規模施設での求人倍率は極めて高い傾向にあります。
東京都内のある特別養護老人ホームでは、2023年度に正職員の介護職を10名募集したところ、半年経っても応募は2名のみでした。
地方の中核都市でも同様に、応募の絶対数が少ない上に、経験者の割合が2割以下という報告もあります。
介護人材の不足は今後ますます加速します。
特に2040年に向けての高齢化のピークに備え、介護職員の「量」だけでなく「質」の確保も急務です。
人材獲得戦略は、業界全体の最優先課題といえるでしょう。
少子高齢化・要介護者増加による構造的な問題
日本は世界で最も速いスピードで高齢化が進んでおり、要介護者も比例して増加しています。
これにより、介護サービスの需要が爆発的に高まっており、慢性的な人材不足を引き起こしています。
総務省統計局「令和6年版 高齢社会白書」によると、2023年時点で日本の65歳以上の高齢者は約3,625万人、総人口の29.1%を占めています。
このような高齢者人口の増加は、労働力人口が減る一方で介護労働力の需要が増す「逆ピラミッド構造」を生み、構造的な人手不足を招いています。
埼玉県のある市では、特別養護老人ホームの新設計画に対して「人員を確保できる見込みがない」として、開設が3年以上延期された事例があります。
これは、単に施設を建てるだけでは介護サービスの提供ができないという現実を示しています。
高齢者人口の増加は、介護業界の人材不足を構造的に進行させています。
要介護者の増加に対し、人材供給が追いつかない状況は、国全体の課題であり、長期的視点での政策と現場改革の両輪が求められます。
離職の理由:身体的・精神的負担と低待遇
介護職の離職理由は主に「身体的負担」「精神的ストレス」「賃金の低さ」の3点に集約されます。
これらが複合的に重なり、離職を引き起こしています。
公益財団法人 介護労働安定センター「令和5年度 介護労働実態調査」では、介護職の離職理由(複数回答)は以下のようになっています。
| 順位 | 離職理由 | 割合(%) |
|---|---|---|
| 1 | 職場の人間関係に問題があったため | 34.3 |
| 2 | 法人や施設・事業所の理念や運営のあり方に不満があったため | 26.3 |
| 3 | 他に良い仕事・職場があったため | 19.9 |
| 4 | 収入が少なかったため | 16.6 |
| 5 | 自分の将来の見込みが立たなかったため | 13.2 |
| 6 | 結婚・妊娠・出産・育児のため | 8.2 |
| 7 | 新しい資格を取ったから | 7.8 |
| 8 | 人員整理・推奨退職など | 6.9 |
| 9 | 家族の介護・看護のため | 4.5 |
| 10 | 自分に向かない仕事だったため | 4.1 |
(注)2019~21年度は介護関係の仕事をしたことがある人の前職を辞めた理由。
2022、23年度は直前職が介護関係だった人の辞めた理由。
介護職の離職理由は、肉体的・精神的・経済的な負担が複合して生じることが多く、単なる「人間関係」だけでは語れません。
根本的な改善には、職場環境の見直しや待遇改善、メンタルヘルス支援が不可欠です。
人材不足の根本原因と対処法

介護職の定着を妨げる主な原因と、それぞれに対する具体的な対処法をわかりやすく解説します。
定着しない主な原因は「労働環境・人間関係・キャリア不安」
介護職の離職・定着困難の主な原因は、以下の3つに分類されます。
それぞれに応じた具体的な対策を講じることで、定着率の向上が期待できます。
定着しない主な原因
- 労働環境の過酷さ
- 人間関係のストレス
- キャリア展望の不透明さ
まず重要なのは、業務の効率化と負担軽減です。
ICT(介護記録ソフト)や介護ロボットを導入することで、職員の身体的・事務的負担を大幅に軽減できます。
無理のないシフト体制の構築や、有給休暇の取得を促す文化の醸成も大切です。
職場内のコミュニケーションの改善には、管理職に対してリーダーシップや傾聴スキルの研修を実施し、部下との関係構築力を高めることが重要です。
資格取得支援制度(受講費補助や研修休暇の付与)を設けると、自己成長を実感できる職場になります。
本人の強みを活かせる配属や、評価制度の透明化もキャリア不安の解消につながります。
職員が安心して働き続けられる環境こそが、離職を防ぎ、人材を定着させる鍵です。
「職場環境」と「職員の声」のギャップに注目する
現場の管理者が「問題はない」と感じていても、職員は不満やストレスを抱えているケースは少なくありません。
この「認識のズレ」が、離職や不信感の原因になります。
「本音が言えない」「フィードバックの機会がない」職場で特に起こりやすく、放置すれば人材流出につながります。
ある法人では、管理職の自己評価では「職場満足度が高い」との認識でしたが、匿名アンケートを実施すると、「上司に相談しても反応が冷たい」、「休憩時間が業務に削られて実質休めていない」といった意見が挙げられました。
このフィードバックを受けて、職場環境改善プロジェクトを立ち上げ、「現場の声を拾う仕組み(対話タイム・提案制度)」を導入した結果、翌年の離職率が前年比30%減少しました。
職場環境の見え方は立場によって大きく異なります。
現場職員のリアルな声に耳を傾け、ギャップを埋めるための「対話と仕組み」が、定着率向上に不可欠です。
離職者データから見る退職理由と改善策の関係性
離職理由は個人差があるように見えて、実際はパターン化されています。
過去の離職者データを分析することで、傾向を「見える化」し、再発防止に活かすことが可能です。
公益財団法人 介護労働安定センター「令和5年度 介護労働実態調査」や複数施設のヒアリングによると、介護職員の離職理由は以下のように分類され、明確な対策と結びついています。
| 離職理由カテゴリ | 主な内容 | 有効な改善策 |
|---|---|---|
| 心身の負担 | 夜勤・重労働・メンタル不調 | 業務分担の最適化、シフト調整、メンタルヘルスケア |
| 人間関係の悪化 | 上司・同僚とのトラブル、相談できない環境 | 1on1ミーティング、外部相談窓口、チームビルディング研修 |
| 処遇の不満 | 給与の低さ、評価不透明 | 昇給ルールの明文化、処遇改善加算の活用 |
| キャリア不安 | 成長実感がない、将来が見えない | キャリアパス制度導入、研修の体系化 |
ポイントは、「何人が辞めたか」ではなく「なぜ辞めたか」に注目することです。
離職は「突然起こるもの」ではなく、日々の小さな不満やズレの蓄積から生じます。
過去の退職理由をデータ化し、改善アクションに落とし込むことで、次の離職を確実に減らすことができます。
「離職データ=経営改善のヒント」と捉え、継続的に向き合うことが重要です。
介護現場で確保すべき人材の考え方

定着率の高い人材を見極めるポイントと、採用時にチェックすべき条件を具体的に解説します。
採用段階で“定着しやすい人材”を見抜くポイントとは?
「すぐ辞めない人」は採用段階である程度見極めが可能です。
ポイントはスキルよりも「価値観・動機・姿勢」。これらを見抜く質問設計と選考基準が必要です。
定着率と採用時の傾向を分析した結果、以下のような因果関係が見られます。
長期定着者の特徴
- 介護職に就く目的が明確
- 大変さをある程度理解している
- 人との関わりが好き
以下のような面接質問項目が、離職傾向のある応募者を見極める助けになります。
| 見極めたい要素 | 質問例 | 見抜けるポイント |
|---|---|---|
| 価値観の一致 | 「なぜ介護職を選んだのですか?」 | 利他的志向・職業理解 |
| ストレス耐性 | 「過去に大変だった仕事とどう向き合いましたか?」 | 忍耐力・自己対処力 |
| 対人姿勢 | 「利用者さんと接するうえで大事にしていることは?」 | 共感力・ホスピタリティ |
また、職場見学や現場体験を選考に組み込むことで、現場とのミスマッチを防げます。
静岡県のグループホームでは、最終面接前に「半日体験勤務」を必須化しました。
現場との相性で辞退が出る一方、入職者の満足度が高く、ミスマッチによる早期離職が大幅に減少しました。
「辞めない人」は偶然ではなく、採用プロセスで見抜ける存在です。
スキルや資格よりも、価値観・目的意識・人間性のマッチを重視した選考を導入することで、長く活躍してくれる人材を確保できます。
スキルだけでなく人間性・価値観のマッチが重要
介護現場においては、経験やスキルよりも「人柄」や「価値観の一致」が職場定着の鍵を握ります。
共感力や協調性、向上心のある人材こそ、長期的に活躍する可能性が高いです。
スキル優先で採用された人材のうち、一定数が早期離職に至る一方で、「人間性に共感した未経験者」が数年定着しているという事例は多数あります。
経験よりも誰と働くか 、何のために働くかを重視する人が増えていることの証拠ともいえます。
千葉県の介護法人では、介護福祉士などの有資格者に偏った採用をしていたが、離職率が高止まりでいた。
そこで「人柄フィット」を重視し、以下の評価軸に変更した結果、離職率は2年で半減しました。
介護は「人と人」の仕事です。
スキルは入職後にも育てられますが、人柄や価値観のミスマッチは修正が困難です。
この人と一緒に働きたいと思える人材こそ、現場に必要な人材といえるでしょう。
現場主導で「求める人材像」を再定義する方法
「求める人材像」は経営側が一方的に決めるのではなく、現場スタッフの声を反映して作成することで、ミスマッチを防ぎ、定着しやすい人材を採用できます。
採用現場でよくある失敗は、「経営側が作った理想像」と「現場が求める実像」が食い違っているケースです。
現場が求めているのは、スキルではなく、以下のような人柄であることが多くあります。
現場スタッフが重視するポイント
- コミュニケーションが丁寧
- 利用者や同僚に敬意を持てる
- 指示待ちでなく、自ら考えて動ける
これらの要素は、従来の履歴書やスキルシートでは判断できません。
求める人材像は、経営の理想論ではなく現場の実感から作る時代です。
現場の定着者に共通する特徴を言語化し、採用活動に反映させることで、「来てほしい人に届く採用」が可能になります。
採用と定着の質を両立するには、「現場×人事」の協働設計が不可欠です。
外国人人材の受け入れと活用戦略

日本の介護・看護・建設・農業など、さまざまな産業において人手不足が深刻化する中、外国人労働者の受け入れは社会の維持に欠かせない課題となっております。
外国人介護人材制度は「特徴と限界」を理解して選ぶべき
外国人を介護現場で受け入れる制度は複数ありますが、それぞれ目的や条件が異なります。
人手不足対策として活用するなら、制度の違いとメリット・デメリットを正しく理解し、現場に合う仕組みを選ぶことが重要です。
外国人が介護現場で働ける主な制度は以下の3つです。
| 制度名 | 主な目的 | 滞在期間 | 日本語要件 | 実務可能範囲 |
|---|---|---|---|---|
| EPA(経済連携協定) | 介護福祉士の国家資格取得支援 | 最大4年(合格で在留資格変更可) | JLPT N3相当以上 | すべての介護業務が可能 |
| 技能実習制度 | 技能移転(開発途上国支援) | 最長5年 | JLPT N4程度(入国前後に研修) | 限定的(身体介護を含むが制限あり) |
| 特定技能(介護) | 介護分野での労働力確保 | 最長5年(延長・永住不可) | JLPT N4相当+介護技能評価試験合格 | ほぼ全般の介護業務が可能 |
東京都の特養施設では、EPA候補者3名が4年間で全員介護福祉士国家試験に合格しました。
語学支援・生活支援を法人全体でサポートした結果、全員が定着し、リーダー候補として育成中です。
外国人介護人材の活用は、「即戦力化」と「支援体制」の両立が成功のカギです。
制度ごとの制約や支援義務を理解したうえで、自法人の体制や受け入れ余力に応じて選ぶことが重要です。
異文化理解と語学支援で定着率を上げるコツ
外国人介護職員の定着には、語学支援だけでなく「文化理解・生活支援」まで包括的にサポートすることが不可欠です。
現場任せにせず、法人全体で取り組む姿勢が成功の分かれ目です。
| 問題 | 有効な対策 | 備考 |
|---|---|---|
| 日本語が通じにくい | 定期的な日本語研修、通訳アプリ活用 | N3~N2レベルまでの育成支援が理想 |
| 指導スタイルの違い | マニュアル+ジェスチャー支援、現場OJTの工夫 | 指導者側の“異文化研修”も重要 |
| 孤立・生活不安 | 生活支援担当者の配置、自治体・地域との連携 | 住居・携帯契約・金融口座なども支援対象 |
大阪府の法人では、外国人職員1人につき「メンター」役を1名日本人職員から選出しました。
住居探し・契約関係・医療案内なども対応しており、就労開始からの離職ゼロ(2年間)を継続中です。
外国人職員の定着は、語学支援だけでは不十分です。
「伝える工夫」+「文化の違いを知る姿勢」+「日常生活まで見守る支援体制」の3点が揃ってはじめて、外国人が辞めない職場が実現できます。
外国人職員を採用するメリットとデメリット
外国人介護人材の採用は、人手不足解消だけでなく、職場に良い刺激と多様性をもたらします。
一方で、語学・文化・定着支援など法人の体制整備が不可欠です。
メリットとリスクのバランスを見極め、準備の有無が成功を左右します。
以下は、外国人職員の採用における主なメリット・デメリットの比較表です。
| 観点 | メリット | デメリット |
|---|---|---|
| 人材確保 | 若く意欲ある人材を確保できる/労働人口減少の対策になる | 言語や文化の壁により即戦力化に時間がかかる |
| 職場の活性化 | 多様な価値観が入り、現場の風通しが良くなる/日本人職員の意識改革 | コミュニケーションのズレや文化的な誤解がトラブル要因に |
| モチベーション | 介護職に憧れや使命感を持って来日する人も多く、向上心が強い | 昇進・キャリアアップの制度が不明瞭だとモチベーション低下の可能性 |
| 経営・制度 | 処遇改善加算や補助金の対象になるケースあり/地域貢献にもつながる | ビザ管理、制度理解、申請業務など事務負担が増す |
愛知県の大型施設では、EPA制度を通じてベトナム人候補者を5名受け入れました。
日本人スタッフとのペア体制と語学支援により、3年後には介護福祉士に全員合格し、リーダー職として活躍中です。
外国人職員の採用は、制度の選定・支援体制・現場教育の3点セットが揃えば、大きな戦力になります。
逆に「人手が足りないからとりあえず雇う」という発想では、トラブルや離職を招くリスクが高くなります。
求人集客・採用強化の実践策

介護人材を採用する際、どの媒体を使うかによって応募数やマッチングの精度、採用スピードが大きく変わります。
求人チャネルは“費用・質・スピード”のバランスで選ぶべき
介護業界の採用では、求人チャネルを使い分けることが大切です。
それぞれの特徴を理解して、自法人に合った戦略を組み立てましょう。
下記は、主な3つの求人チャネルの特徴をまとめた表です。
| 項目 | ハローワーク | 介護専門求人媒体 | 人材紹介 |
|---|---|---|---|
| 費用 | 無料 | 月額掲載料あり(約3万~10万円) | 成功報酬制(年収の20〜30%が一般的) |
| 応募数 | 比較的多め(特に50代以上に強い) | 若年層〜中堅まで幅広くアプローチ可能 | 少数精鋭(面談済の求職者を紹介) |
| スピード感 | 遅め | 中程度 | 早い |
| マッチ度 | 幅広いがミスマッチも多め | 比較的良質だが、自社対応力に左右されるやすい | 高め(条件や人物像に合った人材を紹介してもらえる) |
大阪市の特養では、夜勤可能な人材を急募し、介護専門の人材紹介を活用しました。
ヒアリングを経て2週間で1名を採用し、6ヶ月以上定着してコストを抑えることができました。
求人チャネルは「どこから応募が来るか」ではなく、「どのような人材を・どのタイミングで・どのコストで採りたいのか」をもとに選ぶべきです。
理想的なのは複数チャネルを組み合わせ、季節や人材像に応じて柔軟に切り替える運用です。
採用サイトやLINE活用で応募窓口を広げる
介護職希望者の多くがスマホで情報収集を行う今、採用サイトとLINE公式アカウントの整備は応募数・質ともに大きな差を生む重要ポイントです。
難しい説明より「写真+簡潔な説明+すぐ応募」が求められています。
採用サイトで雰囲気をチェックしてから応募という流れが主流になっています。
また公式LINEからの応募は「ハードルが低く便利」と好評です。
LINEを活用している企業はまだ少なく、多くの法人が採用チャネルの見逃しをしているのが現状です。
千葉県の小規模デイサービスは公式LINEアカウントを開設し、施設紹介・職員インタビュー動画を定期配信しました。
また「LINEで質問→応募」までを1タップ導線にしたところ 6ヶ月で応募数が3倍、問い合わせ対応の手間も削減されました。
LINE公式アカウント活用の基本ステップ
- 採用専用の公式LINEを開設
- 職員インタビュー(できれば動画で)
- 「1日の仕事の流れ」を写真で伝える
- 給与モデル、研修内容、キャリアステップを明記
- よくある質問(Q&A形式で不安払拭)
スマホ導線が整っていない=応募者を逃している可能性が高い時代です。
採用サイトとLINEは、「求人広告だけでは伝えきれない雰囲気と安心感」を補う存在です。
低予算でも始められる手段なので、費用対効果の高い施策として積極的に導入しましょう。
人材獲得に成功した事例と共通点

介護業界では人手不足が深刻化するなかでも、人材獲得に成功している施設があります。
実際に人材確保に成功した施設の取り組みと、その共通点をわかりやすくご紹介します。
SNSや動画活用で応募者数が倍増した施設の例
近年、介護業界でも動画やSNSを通じて職場の雰囲気を見せることで応募数が倍増した施設が続出しています。
紙の求人票や文字情報だけでは伝えられない「安心感・親近感」が、求職者の心を動かしています。
特にInstagramとYouTubeでの効果が顕著です。
福岡県のある施設は、Instagramで応募前の親近感づくりに成功しました。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 背景 | 面接時のミスマッチが多く、応募者との相互理解が不足していた |
| 施策 | ・公式Instagram開設 ・週2回の投稿(レク風景・スタッフ紹介) ・ハイライト機能で「施設のこだわり」などをカテゴリ化 |
| 工夫点 | ・応募前に施設の雰囲気を可視化 ・DMでの事前相談が可能な導線づくり |
| 結果 | ・6ヶ月でフォロワー300名 ・応募者は「Instagramを見て応募」 |
| 効果 | 応募後のミスマッチが大幅に減少 |
「応募が来ない」のではなく、「情報が伝わっていない」だけかもしれません。
SNSや動画を通じて“空気感・人柄・安心感”を伝えられれば、求職者の応募ハードルは驚くほど下がります。
シニア・未経験歓迎戦略で採用層を拡げた実例
介護業界の人手不足を補うためには、「即戦力」や「若年層」に絞った採用から脱却し、シニア層や異業種からの未経験者の受け入れ体制を整えることが重要です。
地方施設ほど若年求職者が少なく、競合も激しくなります。
定着率は「年齢」よりも「職場との相性」と「働きやすさ」が大きく影響します。
大阪府のある施設では、元事務職の50代男性を採用し、職場改善にも貢献しました。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 背景 | 男性介護職員が少なく、夜勤や力仕事のシフトに偏りが出ていた |
| 施策 | ・求人に「未経験歓迎」「デスクワーク経験活かせます」と明記 |
| 結果 | ・業務改善や周囲との連携に貢献 |
| 効果 | ・男性職員が加わったことでシフトが安定 ・チームの柔軟性が向上 |
多様な人材の活用は、人手不足解消だけでなく、利用者との関係性の質向上にもつながります
まとめ
介護業界の人材不足は深刻ですが、SNSや動画で職場の雰囲気を伝えたり、シニアや未経験者の積極採用で採用層を広げることで応募数が大幅に増加します。
さらに、職員の声を反映し働きやすい環境づくりに注力することで離職率を下げ、採用コストを抑えられます。
採用だけでなく「辞めない職場づくり」が根本解決のカギです。