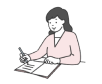企業が知るべき!外国人採用断り方の正解は?

企業が知るべき!外国人採用断り方の正解は?

外国人応募者への採用対応やお断りに悩んだ経験はありませんか?
適切な対応ができないと、企業の信頼を損なったり、法的リスクに発展する可能性があります。
一方で、誠実で配慮のある対応は、企業ブランドを守り、多様性を活かした成長にも繋がります。
本記事では、外国人応募者への公正な採用基準の作り方やお断りメールの書き方、避けるべき事例とその解決法を具体的に解説します。
信頼と多様性を重視した採用術で、企業の未来を切り拓きましょう。
本記事のポイント
- 外国人応募者への適切な採用プロセスの確立
- 外国人応募者へのお断りメール文例
- 企業の採用ポリシー見直し方法
外国人応募者への適切な採用お断り

外国人応募者への採用お断りの際は、丁寧で配慮のある表現を使用することが重要です。
公平で透明性のある採用プロセスの確立
公平で透明性のある採用プロセスは、企業の信頼性を高め、優秀な人材を引き寄せる基盤となります。
信採用プロセスの透明性は、応募者に対して企業の誠実さを示し、信頼感を醸成します。
公平な選考基準は、多様なバックグラウンドを持つ人材の採用を可能にし、組織の創造性と革新性を高めます。
あるテクノロジースタートアップ企業では、ブロックチェーン技術を採用プロセスに導入し、全ての採用ステップを記録することで透明性を確保しました。
その結果、公平な採用活動が実現し、採用コストを30%削減することができました。
透明性と公平性を備えた採用プロセスは、企業の信頼性を高め、多様な人材を引き寄せる要因となります。
採用拒否が企業イメージに与える影響
不適切な採用拒否は、企業の評判を損ない、将来的な人材確保やビジネスチャンスに悪影響を及ぼす可能性があります。
採用拒否の際に差別的な対応や不透明な理由を示すと、SNSや口コミで企業の評判が低下するリスクがあります。
不当な採用拒否は、法的なトラブルを引き起こし、企業の信頼性を損なう可能性があります。
ある企業が、採用プロセスでの不適切な対応がSNSで拡散され、消費者からの信頼を失い、売上が減少したケースがあります。
採用拒否の際は、適切で透明性のある対応を行うことで、企業イメージの低下を防ぐことが重要です。
法的観点から見る外国人応募者への対応
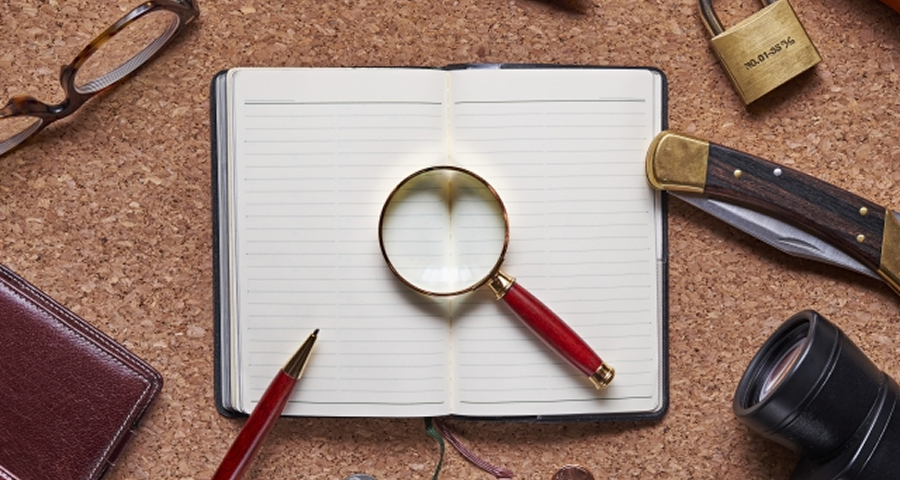
外国人応募者への対応においては、法的観点から慎重に対応することが求められます。
特に、雇用に関する法令やビザの要件など、外国籍の方を雇用する際には守るべきルールが多岐にわたります。
日本における外国人労働者関連の法律概要
日本では、外国人労働者の雇用に関して、労働基準法や職業安定法などが適用され、国籍や人種を理由とした差別的取扱いは禁止されています。
ある企業が、採用プロセスで外国人応募者に対して国籍を理由に不採用とした場合、職業安定法第3条に違反する可能性があります。
日本の法律は、外国人労働者に対する差別的取扱いを禁止しており、企業はこれらの法律を遵守する必要があります。
外国人採用で「断り方」を間違えるとどうなるか
外国人採用における不採用通知の伝え方を誤ると、法律違反による罰則や損害賠償請求といった深刻な法的トラブルに発展するリスクがあります。
特に「外国人であること」を理由とした不採用は、明確な差別行為と見なされ、企業の信頼を著しく損なう結果を招きます。
外国人採用で注意すべき法律(雇用対策法、労働基準法)と差別と見なされるケース
不採用の理由として国籍や人種を挙げることは、雇用対策法や労働基準法に抵触する可能性が極めて高いです。
採用選考は、あくまで応募者の能力や適性に基づいて行わなければなりません。
外国人応募者を不採用にする際に注意すべき法律
- 雇用対策法 第10条: 事業主は、労働者の募集及び採用について、その年齢にかかわりなく均等な機会を与えなければならないと定めています。この趣旨は国籍に関しても同様に適用されると解釈されており、「外国籍」を理由に一律に不採用とすることは、この均等な機会の提供に反する可能性があります。
- 労働基準法 第3条: 使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならないと定めています。採用は労働条件の入り口であり、国籍を理由とした不採用は、この条文の趣旨に反する差別的取扱いの第一歩と見なされる可能性があります。
- 厚生労働省の指針: 厚生労働省は「公正な採用選考の基本」の中で、採用選考時に配慮すべき事項として「人種、民族、社会的身分、門地、本籍、出生地その他社会的差別の原因となるおそれのある事項」などを挙げており、国籍を理由とした不採用はこれに該当します。
法律と国の指針は、国籍を理由とした不採用を明確に禁じています。採用担当者は、法律違反のリスクを避けるため、応募者の国籍ではなく、あくまで職務遂行に必要な能力と適性のみを評価基準としなければなりません。
「外国人だから」という理由はNG!公正な採用選考の重要性
「外国人だから」という曖昧な理由での不採用は、差別と受け取られ、企業の評判を落とすだけでなく、訴訟リスクも伴います。
採用のミスマッチを防ぎ、優秀な人材を確保するためにも、公正な基準に基づいた採用選考が不可欠です。
外国人応募者に対する公正な選考とは
- 明確な採用基準の設定: 募集職種に必要なスキル、経験、資格などを具体的に定め、その基準に基づいて全応募者を評価する。
- 構造化面接の導入: 全ての候補者に同じ質問を同じ順番で行い、評価基準を統一することで、面接官の主観によるブレをなくす。
- 国籍を問わない書類選考: 応募書類から国籍や顔写真といった情報を隠して(ブラインド選考)、純粋に経歴やスキルだけで一次選考を行う。
公正な採用選考は、法的リスクを回避するだけでなく、多様な人材の中から真に企業に貢献できる優秀な人物を見つけ出すための最良の手段です。
採用基準を明確化し、誰に対しても公平なプロセスを徹底することが、企業の持続的な成長に繋がります。
在留資格やビザ申請中の外国人応募者への対応と注意点
応募者が希望する職務内容と、保有(または申請中)の在留資格で認められる活動内容が合致しない場合、不採用とすること自体に法的な問題はありません。
ただし、その伝え方には細心の注意が必要です。
| 状況 | 適切な対応・伝え方 | 不適切な対応・伝え方 |
| 就労不可の在留資格(例:留学、短期滞在)しか保有していない | 「誠に恐縮ながら、今回ご応募いただいた職務内容では、現在の在留資格ではご就業いただくことが難しいと判断いたしました。」 | 「ビザがない方は採用できません。」 |
| 在留資格の活動内容と業務内容が不一致 | 「貴殿の在留資格『技術・人文知識・国際業務』では、当社の募集職種である『単純作業』に従事いただくことが法律上認められておりません。」 | 「あなたのビザではうちの仕事は無理です。」 |
| 在留資格認定証明書を申請中 | 「選考の結果、今回は誠に残念ながら採用を見送らせていただくこととなりました。なお、在留資格の件とは一切関係ございません。」(※他のスキル面などで判断した場合) | 「ビザが下りるか分からないので不採用にします。」 |
在留資格を理由に不採用とする場合は、「国籍」ではなく「法律上の要件」として、客観的な事実のみを伝えることが重要です。
誤解を招かないよう、丁寧かつ具体的な言葉を選んで説明する必要があります。
外国人応募者へのお断りメールの作成ポイント

外国人応募者へのお断りメールを作成する際のポイントは、丁寧で配慮のある表現を使い、応募者が不快に感じないようにすることが大切です。
メール作成で意識すべき基本マナー
お断りメールは、応募者への感謝と敬意を示し、企業の信頼性を維持するために、丁寧で配慮のある表現を用いることが重要です。
適切な対応は、応募者に対する企業の誠実さを伝え、ブランドイメージを損なわないために必要です。
不適切な表現や対応は、差別的と受け取られ、法的トラブルの原因となる可能性があります。
ある企業が形式的で冷たいお断りメールを送った結果、応募者からの評価が低下し、SNS上で企業イメージが損なわれたケースがあります。
お断りメールは、応募者への感謝と敬意を込め、丁寧で配慮のある表現を心掛けることで、企業の信頼性と評判を守ることができます。
応募への感謝を適切に伝える方法
応募者が時間と労力を費やして応募してくれたことに対し、真摯な感謝の意を伝えることは、応募者の満足度を高め、企業の印象を良くします。
感謝の意を示すことで、応募者の努力を認め、企業の誠実さを伝えます。
丁寧な対応は、将来的な応募や顧客としての関係性を築く基盤となります。
「この度は弊社の求人にご応募いただき、誠にありがとうございました。」といった感謝の表現を用いることで、応募者に好印象を与えた企業があります。
応募者への感謝の意を適切に伝えることで、企業の誠実さを示し、良好な関係性を築くことが可能です。
丁寧かつ簡潔なお断りの理由の伝え方
お断りの理由は、具体的すぎず、一般的な表現で簡潔に伝えることが望ましいです。
具体的な理由は、応募者の自尊心を傷つける可能性があるため、一般的な表現で伝えることが適切です。
詳細な理由を伝えることで、差別的と受け取られるリスクを避けることができます。
「慎重に選考を進めさせていただきましたが、今回はご期待に沿えない結果となりました。」といった表現を用いることで、応募者への配慮を示した企業があります。
お断りの理由は、丁寧で一般的な表現を用いて簡潔に伝えることで、応募者への配慮と法的リスクの回避が可能です。
お断りの理由を明確にするリスク
お断りの理由を詳細に伝えることは、応募者の感情を害し、法的トラブルを引き起こす可能性があるため、避けるべきです。
ある企業が具体的な不採用理由を伝えた結果、応募者からのクレームや法的措置を取られる事態となったケースがあります。
お断りの理由は、詳細に伝えすぎず、一般的な表現で簡潔に伝えることが、リスク回避のために重要です。
外国人応募者へのお断りメール文例
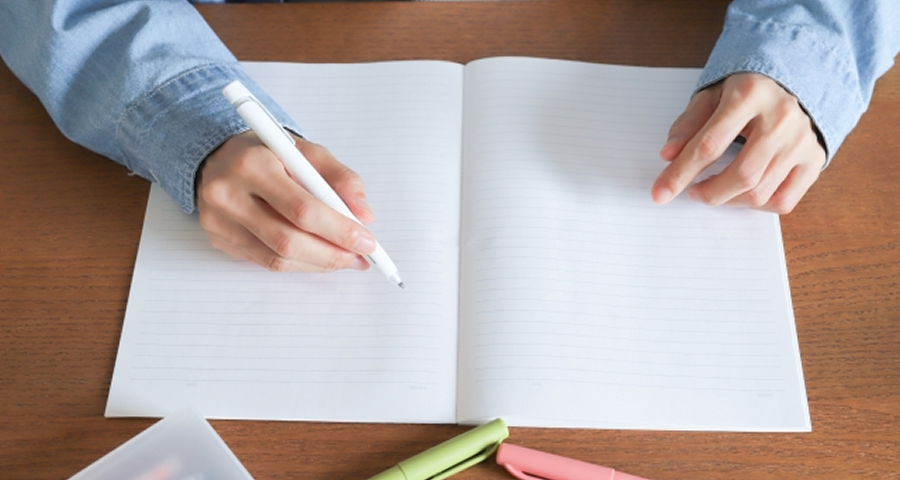
外国人応募者へのお断りメールは、選考の結果を伝える際に、相手に対して敬意を払いながら配慮をもって対応することが重要です。
特に外国籍の応募者の場合、ビザの要件や労働条件に関する理由が影響することも多いため、透明で理解しやすい説明を心がけることが求められます。
基本の不採用通知メールテンプレート(日本語・英語)
不採用通知の基本構成は、「応募への感謝」「選考結果」「残念な結果であること」「今後の活躍を祈る言葉」です。
日本語でも英語でも、この構成を丁寧に伝えることが大切です。
日本語テンプレート
件名:選考結果のご連絡【株式会社〇〇】
〇〇様
この度は、数ある企業の中から当社の〇〇職にご応募いただき、誠にありがとうございました。
厳正なる選考の結果、誠に残念ながら、今回はご期待に沿いかねる結果となりました。何卒ご了承くださいますようお願い申し上げます。
ご提出いただきました応募書類につきましては、当社の個人情報保護方針に基づき、責任を持って破棄させていただきます。
末筆ではございますが、〇〇様の今後のご健勝とご活躍を心よりお祈り申し上げます。
英語テンプレート
Subject: Regarding your application for the [Position Name] position at [Company Name]
Dear [Applicant Name],
Thank you for your interest in the [Position Name] position at [Company Name] and for taking the time to interview with our team.
We received a large number of applications, and after careful consideration, we have decided to move forward with other candidates at this time. This was a difficult decision, as we were impressed with your skills and qualifications.
We will keep your resume on file for future openings that may be a better fit.
We wish you the best of luck in your job search.
Sincerely,
The [Company Name] Hiring Team
テンプレートを活用しつつも、感謝の気持ちを真摯に伝えることが重要です。
応募者のプライバシーに配慮し、応募書類の取り扱いについても明記することで、誠実な企業姿勢を示すことができます。
応募資格を満たしていない場合の文例
応募資格を満たしていない場合は、応募者への感謝を述べつつ、不採用理由を簡潔に伝えることが重要です。
応募資格を満たしていない場合でも、応募者の努力に敬意を示すことで、企業イメージの向上につながります。
詳細な理由を伝えすぎると、応募者の感情を害する可能性があるため、簡潔さが求められます。
メール文例
件名: 選考結果のご連絡
この度は、弊社の〇〇職にご応募いただき、誠にありがとうございました。
応募書類を拝見し、慎重に検討させていただきましたが、誠に残念ながら、今回のポジションの応募資格を満たしていないため、採用を見送らせていただくこととなりました。
貴重な時間を割いてご応募いただきましたこと、心より感謝申し上げます。
今後のご活躍をお祈り申し上げます。
〇〇株式会社 採用担当
応募資格に基づくお断りの場合は、感謝と簡潔な理由を伝えることで、誠実さを示すことが可能です。
採用枠が埋まった場合のお断り文例
採用枠の充足を理由にする場合、応募者が悪いわけではないことを伝えることで、納得感を高められます。
採用枠が埋まった場合は、応募者個人への否定ではなく、状況による判断であることを示す必要があります。
メール文例
件名: 採用枠充足による選考結果のご連絡
この度は、弊社の〇〇職にご応募いただき、誠にありがとうございました。
選考の結果、採用枠が既に充足しているため、今回は残念ながら貴殿を採用することが叶いませんでした。
貴重なお時間をいただきましたこと、深く感謝申し上げます。
また機会がございましたら、ぜひ再度ご応募いただけますと幸いです。
今後のご活躍をお祈りしております。
〇〇株式会社 採用担当
採用枠充足の場合は、状況による結果であることを明確にすることで、応募者の納得感を得られます。
他の候補者との比較結果によるお断り文例
他の候補者を選んだ場合、選考プロセスの難しさを伝えることで、応募者の努力を評価できます。
「選考が接戦であった」と伝えることで、応募者の能力が評価されていると感じさせることができます。
同様の事例では、応募者が企業への信頼を損なわず、別のポジションで再応募するケースが増えています。
メール文例
件名: 選考結果のご連絡
この度は、弊社の〇〇職にご応募いただき、誠にありがとうございました。
書類選考および面接を通じて慎重に検討させていただきましたが、今回は他の候補者を採用する運びとなりました。
〇〇様のご経験やスキルは大変素晴らしいものであり、選考は非常に難しい判断となりましたことをお伝えさせていただきます。
また機会がございましたら、ぜひご応募いただけますと幸いです。
今後のご健勝とご活躍をお祈り申し上げます。
〇〇株式会社 採用担当
他の候補者との比較結果の場合、応募者の努力やスキルを評価する表現を用いることで、誠実な印象を与えることができます。
応募者へのポジティブなフィードバックを添える例
ポジティブなフィードバックを添えることで、応募者の成長を促し、企業への信頼を深めることが可能です。
応募者が得たフィードバックを今後のキャリアに活かせるようにすることで、企業の印象を向上させます。
ポジティブなメッセージは、応募者の心理的負担を軽減し、良好な関係構築に繋がります。
メール例文
件名: 選考結果のご連絡
この度は、弊社の〇〇職にご応募いただき、誠にありがとうございました。
厳正なる選考の結果、今回は貴殿を採用することが叶いませんでしたが、貴殿のスキルやご経験には非常に感銘を受けました。
特に〇〇における実績は素晴らしく、今後のキャリアで必ずや大きな成果を挙げられるものと確信しております。
また別の機会でお会いできることを心より楽しみにしております。
今後のさらなるご活躍をお祈り申し上げます。
〇〇株式会社 採用担当
ポジティブなフィードバックを添えることで、応募者に対する配慮を示し、企業への信頼を深めることができます。
【トラブル防止】人材紹介会社やハローワーク経由の断り方

人材紹介会社やハローワークを通じて応募があった場合、不採用の連絡は必ず紹介元(エージェントや職員)を通して行い、応募者本人に直接連絡してはいけません。
これがトラブルを未然に防ぐための鉄則です。
紹介元担当者への伝え方とマナー
紹介元の担当者には、できるだけ早く、そして具体的なフィードバックを添えて不採用の連絡をすることがマナーです。
これにより、担当者との信頼関係を維持し、今後の人材紹介の精度向上にも繋がります。
契約内容を遵守することは、コンプライアンスの観点からも重要です。
外国人応募者紹介元への連絡ポイント
連絡のタイミング: 面接後、2〜3営業日以内を目安に連絡するのが理想です。遅くとも1週間以内には連絡しましょう。
連絡方法: 基本的には電話で第一報を入れ、その後メールで正式に通知すると丁寧です。
伝える内容:応募してくれた候補者を紹介してくれたことへの感謝と具体的な不採用理由(例:「〇〇のスキルが、今回の要件レベルに一歩及ばなかった」「コミュニケーション能力は高いが、求める専門知識の点で他の候補者に軍配が上がった」など)
紹介元の担当者は、企業の採用活動における重要なパートナーです。
外国人応募者の評価だけでなく、パートナーとして敬意を払い、誠実なコミュニケーションを心がけることが、長期的に見て企業の採用力を高めることに繋がります。
やむを得ず内定を取り消す場合の手続きと注意点

内定の通知をもって労働契約が成立したと見なされるため、企業側からの一方的な内定取り消しは「解雇」に相当します。
客観的に見て合理的で、社会通念上相当と認められる重大な理由がなければ、内定取り消しは無効となり、損害賠償を請求されるリスクがあります。
- 判例(大日本印刷事件 最高裁 S54.7.20): この判例により、「採用内定の通知により、就労の始期を定め、それまでの間に労働契約を解約できる権利を留保した労働契約が成立した」という考え方が確立されました。
- 労働契約法 第16条(解雇): 「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする」と定められており、これは内定取り消しにも適用されます。
| 認められる可能性があるケース(極めて限定的) | 認められないケース |
| 内定者が卒業できなかった場合 | 景気が悪化した、業績が下がった |
| 経歴詐称が発覚した場合 | 他にもっと良い人材が見つかった |
| 健康状態が著しく悪化し、就労が困難になった場合 | 「会社の雰囲気に合わない気がしてきた」といった主観的な理由 |
| 在留資格が不交付となった場合 |
内定取り消しは、最終手段中の最終手段です。
実行する前に、必ず弁護士などの法律専門家に相談し、その妥当性を慎重に検討してください。
安易な内定取り消しは、企業の存続に関わるほどの大きな法的・社会的ダメージに繋がる可能性があります。
就労ビザ申請を取り下げる際の手順
内定取り消しや内定辞退により、申請済みの在留資格認定証明書(COE)が不要になった場合は、速やかに出入国在留管理庁(入管)に対して申請の取り下げ手続きを行う必要があります。
虚偽の申請を防ぎ、入管の審査業務を円滑に進めるために、申請の取り下げは企業の義務と言えます。
この手続きを怠ると、今後のビザ申請において、企業自体の信頼性が疑われ、審査が厳しくなる可能性があります。
申請を取り下げないと、元内定者の個人情報が入管に残り続けることになります。
プライバシー保護の観点からも、不要になった申請は速やかに取り下げるべきです。
就労ビザ申請取り下げ手続きの方法
- 必要書類の準備:
- 申請取下書(任意の書式で作成可能。申請人の氏名、国籍、生年月日、申請年月日、申請受付番号などを記載し、「申請を取り下げます」という旨を明記し、会社の記名押印をする)
- 受理票(申請時に受け取ったもの)のコピー
- 提出:
- 申請を行った地方出入国在留管理局の窓口に持参するか、郵送で提出
就労ビザ申請の取り下げは、採用活動の最後の締めくくりとして、忘れずに行うべき重要な手続きです。
この誠実な対応が、将来の円滑な外国人採用に繋がります。手続き自体は複雑ではありませんので、速やかに対応しましょう。
外国人応募者への対応で避けるべき事例

外国人応募者に対して適切な対応を行うことは、企業のブランドイメージや多様性の尊重に大きく影響します。
差別的と受け取られる表現の具体例
採用プロセスにおいて、国籍や人種、宗教などに基づく差別的な表現は厳禁であり、企業の信頼性を損なう可能性があります。
日本の労働基準法第3条では、使用者が労働者の国籍、信条、または社会的身分を理由として差別的取扱いをしてはならないと規定されています。
差別的な表現は、社会的非難を招き、企業のブランド価値や信頼性を低下させるリスクがあります。
ある企業が採用面接で「日本語が母国語でないと難しい」と発言し、応募者から差別的と指摘され、SNSで批判が拡散されたケースがあります。
採用時のコミュニケーションでは、応募者の多様性を尊重し、差別的と受け取られる表現を避けることが重要です。
無回答や曖昧な対応によるトラブル事例
応募者からの問い合わせや応募に対して無回答や曖昧な対応を行うと、誤解や不信感を招き、企業の評判を損なう可能性があります。
明確で迅速な対応は、応募者との信頼関係を築く上で不可欠です。
曖昧な対応は、応募者に不安や不満を与え、SNSなどでのネガティブな発信につながるリスクがあります。
ある企業が応募者からの問い合わせに対し、長期間回答をしなかったため、応募者がSNSで不満を表明し、企業の評判が低下したケースがあります。
応募者への対応は、迅速かつ明確に行い、無回答や曖昧な対応を避けることで、信頼性を維持することが重要です。
不適切な対応が企業にもたらした影響事例
採用プロセスでの不適切な対応は、法的トラブルや企業イメージの失墜など、深刻な影響をもたらす可能性があります。
差別的な対応や不適切な労働条件の提示は、労働基準監督署からの指導や訴訟リスクを高めます。
不適切な対応が公になると、消費者や取引先からの信頼を失い、業績に悪影響を及ぼす可能性があります。
ある企業が外国人労働者に対し、労働基準法を無視した長時間労働を強いた結果、労働基準監督署から指導勧告を受け、社会的信用を失ったケースがあります。
採用プロセスにおける適切な対応は、法的リスクの回避と企業の信頼性維持のために不可欠です。
企業としての採用ポリシーの見直しと改善

企業としての採用ポリシーを見直し、改善することは、より多様で柔軟性のある人材を確保するために重要です。
採用ポリシーを見直すことにより、企業の成長を加速し、労働市場の変化に適応できる組織を作り上げることができます。
公正な採用基準を設定するためのステップ
公正な採用基準を設定するには、現場のニーズを把握し、活躍する社員の共通点を分析し、評価項目を明確化することが重要です。
ある企業では、現場社員へのヒアリングを通じて必要なスキルセットを洗い出し、活躍社員の共通点を分析することで、具体的な評価項目を設定し、採用ミスマッチの減少に成功しました。
公正な採用基準の設定は、現場の声を反映し、具体的な評価項目を明確にすることで、採用の精度と公平性を高めることができます。
社内教育で差別や偏見を排除する方法
社内教育を通じて、社員一人ひとりが無意識の偏見に気づき、多様性を尊重する意識を醸成することが重要です。
人は知らず知らずのうちに偏見を持つことがあり、これが差別的な行動につながる可能性があります。
多様な価値観や背景を持つ人々と協働することで、組織の創造性や柔軟性が向上します。
ある企業では、全社員を対象に多様性とインクルージョンに関する研修を実施し、無意識の偏見に気づくワークショップを行うことで、社内の差別的な言動が減少し、職場環境の改善が見られました。
社内教育を通じて、社員が無意識の偏見に気づき、多様性を尊重する文化を築くことが、差別や偏見の排除につながります。
外国人応募者への対応体制を整えるメリット
外国人応募者への適切な対応体制を整えることで、優秀な人材の確保や企業の国際的な競争力の強化が期待できます。
多様なバックグラウンドを持つ人材を採用することで、労働力不足の解消につながります。
異なる文化や価値観を持つ人材が加わることで、組織のイノベーションが促進されます。
ある製造業の企業では、外国人技術者を積極的に採用し、彼らの専門知識や異なる視点を活用することで、新製品の開発に成功し、海外市場への進出も果たしました。
外国人応募者への対応体制を整えることは、組織の多様性を高め、競争力の強化につながります。
採用後のフォローアップ体制の重要性
採用後の適切なフォローアップ体制は、社員の定着率向上と早期戦力化に寄与します。
あるIT企業では、入社後3ヶ月間のメンター制度を導入し、新入社員の疑問や不安を解消するサポートを行った結果、定着率が向上し、プロジェクトへの早期参画が可能となりました。
まとめ
外国人応募者への対応は、企業の信頼性と多様性を高める鍵です。
公正な採用基準を設定し、差別や偏見を排除する社内教育を行うことで、透明性と公平性を確保できます。
また、応募者へのお断りメールでは感謝を伝えつつ簡潔で配慮のある表現を心がけるべきです。
採用後のフォローアップ体制を整えることで定着率を高め、新たな視点やスキルを活用して企業の競争力を向上させましょう。
適切な対応が法的リスクの回避と企業ブランドの強化に繋がります。