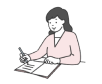企業の人手不足解消法とは?効果的な対策と実践例を紹介

企業の人手不足解消法とは?効果的な対策と実践例を紹介

企業の人手不足は、少子高齢化や新型コロナウイルスの影響など、さまざまな要因から深刻化しています。
生産性低下や労働環境の悪化を防ぐためには、効率的な業務の自動化やスキルアップ、多様な人材の活用が必要です。
この記事では、企業が人手不足を解消するために取り組むべき具体策を解説します。
この記事のポイント
- 企業が人手不足な理由
- 企業の従業員の満足度を上げるには
- 労働市場における最新アプローチ
なぜ企業は人手不足に直面しているのか?

現在、多くの企業が人手不足に直面しており、これは日本をはじめとする多くの国々で深刻な問題となっています。
企業がこのような状況に直面する理由は、単に労働市場の需給バランスの問題だけでなく、さまざまな社会的、経済的要因が複雑に絡み合っています。
少子化の進行と出生率の低下
少子化が進行する中で、新しい労働力の供給が不足しており、企業が必要とする人材が確保できなくなっています。
日本の出生率は低下しており、今後も減少が続くと予測されています。
これにより、働き手となる若年層の数が減少し、企業は新規の労働力を得ることがますます難しくなっています。
少子化の進行が労働市場における供給不足を引き起こし、企業は人手を確保するのがますます困難になっています。
高齢者の増加と退職者数の増加
高齢化社会が進行し、退職者数が増加することで、労働市場における人手不足が深刻化しています。
日本では高齢化が進み、65歳以上の高齢者の人口は増加しています。
一方で、定年退職する高齢者の数が増加しており、それに伴い企業は後継者を確保できずに困難な状況に直面しています。
特に介護業界や医療業界では、退職する高齢者を補う若い世代が不足しており、求人倍率が高くなっています。
高齢化と退職者数の増加により、企業は人手を確保するのが難しくなっており、後継者の育成が急務となっています。
新型コロナウイルスの影響
新型コロナウイルスの影響で、労働力が一時的に減少し、企業の事業活動に支障をきたしました。
コロナ禍による緊急事態宣言や外出自粛などが影響し、多くの企業が業務を一時的に停止しました。
多くの従業員が休業やリモートワークに移行したことが、労働力の一時的な減少を引き起こしました。
飲食業や観光業など、外出制限に影響された業界では、営業を再開したものの、スタッフ不足が問題となり、営業の再開が困難になった事例があります。
コロナウイルスの影響で、企業は短期間で人手不足に直面し、その影響は現在も続いています。
労働市場における変化と不安定な雇用状況
新型コロナウイルスは労働市場に変化をもたらし、雇用の不安定さを引き起こしています。
不況や企業の縮小により、非正規雇用や契約社員の雇用が増加しています。
特にサービス業や小売業では、パートタイムの求人が増え、正社員の採用が難しくなっています。
労働市場の不安定化により、企業は人材の確保に課題を抱えるようになり、特に非正規雇用の増加が企業経営に影響を与えています。
リモートワークの普及が業種間の労働需要に格差を生じさせ、その影響を受ける業界では今後の人手不足が深刻化するでしょう。
求人倍率の増加と労働市場の変化
求人倍率が上昇しており、企業間での採用競争が激化しています。
近年、日本の求人倍率は上昇しており、求職者1人に対して企業の求人が増えている状況です。
特に、2020年以降のコロナ禍からの景気回復や働き方改革の影響で、企業が求人を出す数が増加しました。
しかし、労働人口の減少と相まって、企業は人材の確保が困難になり、競争が激しくなっています。
例えば、IT業界や製造業などの人手不足が深刻な業界では、求人に対して応募が少ないため、採用難易度が高くなっています。
企業は給与を上げたり、待遇を改善したりして、採用活動に力を入れています。
求人倍率の上昇により、企業間で採用競争が激化しており、企業は採用活動においてより多くのリソースを投入し、求人条件を見直す必要があります。
特定の業種における人手不足の深刻化
特定の業種では人手不足が特に深刻化しており、企業が求める人材を確保できない状況が続いています。
製造業、介護業、IT業界などでは、特に人手不足が顕著です。これらの業界は専門的なスキルを持つ人材を求めているため、求人に対する応募者数が不足しがちです。
また、高齢化の進行に伴い、介護業界では介護職の人手不足が深刻です。
例えば、製造業では技術職の人手不足が深刻化し、企業は高い給与や福利厚生の提供により、他社と競り合っています。
介護業界では、低賃金や過酷な労働環境が応募者数に影響を与えています。
特定の業種では依然として人手不足が解消されず、企業は業界特有の採用難を乗り越えるために、待遇や働き方の見直しを行う必要があります。
人手不足が企業に与える影響

人手不足は、企業にとって単なる一時的な困難にとどまらず、長期的な成長や競争力にも大きな影響を及ぼします。
生産性の低下と業務の遅延
人手不足が続くと、業務が滞り、生産性が低下します。
人員不足により、限られたスタッフに業務が集中し、対応できる業務の量に限界があります。
これにより、タスクが後回しにされ、業務進行に遅れが生じます。
さらに、対応する業務量が増えるため、品質が低下する恐れもあります。
例えば、小売業では、従業員数が不足しているため、商品補充や在庫管理が遅れ、販売機会を逃すことが多くなっています。
業務の遅れは他の業務にも波及し、全体の生産性が低下します。
人手不足が続くと、業務が滞り、全体の生産性に悪影響を及ぼします。
企業は効率的な業務の進行を維持するために、適切な人員配置と業務管理が必要です。
顧客対応の遅延やサービス品質の低下
顧客対応の遅延やサービス品質の低下が顧客満足度に影響を与えます。
人手不足によって、顧客からの問い合わせ対応や商品・サービスの提供が遅れ、結果的にサービス品質が低下します。
顧客満足度が低下すると、リピート客の減少や新規顧客の獲得に影響を及ぼします。
例えば、レストラン業界では以下の事態が発生しています。
| 影響 | 詳細 |
|---|---|
| 注文受付の遅延 | 従業員不足により、注文を受けるまでの時間が長くなり、顧客の待機時間が増加。 |
| 料理提供時間の長期化 | 厨房スタッフやサービススタッフが不足し、料理の準備や提供に時間がかかる。 |
| 顧客からの苦情増加 | 提供が遅れることにより、顧客の不満が高まり、苦情が増加。 |
| サービス品質の低下 | スタッフが多忙で、一部の顧客対応が雑になったり、サービスが行き届かなくなる。 |
| 売上減少 | 顧客の不満が溜まり、再訪客が減少し、最終的に売上に悪影響を与える可能性がある。 |
顧客対応の遅延やサービス品質の低下は企業の評判に直結し、売上に悪影響を与えるため、早急に対応策を講じる必要があります。
長時間労働と過労による健康リスク
長時間労働や過労は従業員の健康リスクを増加させ、企業にとっても大きなコストとなります。
人手不足により、従業員に過剰な業務が割り当てられ、長時間労働が常態化すると、身体的・精神的な健康リスクが高まります。
過労やストレスは病気や事故につながる恐れがあります。
例えば、介護業界では、従業員の不足から長時間労働が続き、過労が原因で休職するケースが増加しています。
これにより、企業は医療費や休職に伴うコストを負担しなければならなくなります。
長時間労働を改善し、従業員の健康を守ることが企業の持続的成長に欠かせません。
ストレスや離職率の増加
従業員のストレス増加と離職率の増加は、企業の生産性と安定性に大きな影響を与えます。
人手不足が続くと、従業員は過重な負担を抱え、ストレスが蓄積します。
このストレスが原因で離職者が増加し、採用活動や再トレーニングにかかるコストが増大します。
例えば、IT業界では人手不足により業務が逼迫し、従業員の離職率が高まっています。
これにより、企業は採用・教育のコストが増加し、安定的な運営が難しくなっています。
ストレスや離職率を低減するためには、労働環境の改善が不可欠です。
売上や利益への影響
労働力不足は生産能力の低下を招き、売上に悪影響を及ぼします。
人手が足りないと、生産ラインやサービスの提供が滞り、売上機会を逃すことになります。
特に、需要が急増している時期に人手が不足すると、大きな機会損失を生む可能性があります。
製造業の企業では、従業員不足のため生産量が減少し、需要に対応できないことが売上減少につながっています。
人手不足を解消し、生産能力を維持することが売上向上には欠かせません。
コスト増加と利益圧迫
人手不足は企業のコストを増加させ、利益を圧迫します。
採用活動や人材確保のためにコストがかかるだけでなく、労働時間の増加や業務の効率化に対する投資が必要になるため、企業の利益が圧迫されます。
IT企業では、プロジェクトの進行が遅れ、追加の労働力を投入するためにコストが増加し、結果として利益が減少しています。
人手不足を解消するためには、コスト管理と効率的な業務の進行が必要です。
人手不足の解消に向けた企業の取り組み
労働力確保のための採用戦略
採用ターゲットを多様化し、さまざまなバックグラウンドを持つ人材を受け入れることで、人手不足の解消に繋がります。
従来の採用対象にこだわらず、多様な人材を採用することで新たな視点やスキルを企業にもたらすことができます。
特に、女性、高年齢者、障害者、外国人など、ターゲットを広げることは、社会的な貢献にもつながり、企業にとって新しい市場を開拓することにも繋がります。
例えば、製造業では、女性や高年齢者の積極的な採用を進めた企業が、生産ラインの多様化に成功し、業務効率が向上した事例があります。
採用のターゲットを広げ、多様な人材を受け入れることは、人手不足の解消に重要な戦略です。
新卒採用・中途採用・派遣社員のバランスを取る
新卒、中途、派遣社員をバランスよく採用することで、柔軟な人材確保が可能になります。
新卒は長期的な成長が見込める一方で、中途採用は即戦力が求められます。
派遣社員は、短期的な人手不足を迅速に補うために有効な手段です。
このバランスを取ることで、企業は必要な人材をタイムリーに確保できます。
IT企業では、即戦力となる中途採用と、将来性を見込んだ新卒採用を並行して行い、業務の安定性を確保している事例があります。
新卒、中途、派遣社員をうまくバランスを取って採用することで、企業の人手不足問題を効果的に解決できます。
働き方改革と労働環境の改善
柔軟な勤務形態を導入することで、社員の満足度を高め、人手不足の解消に貢献します。
フレックスタイムやリモートワークは、従業員にとって働きやすい環境を提供し、ライフスタイルに合わせた働き方ができるようになります。
この柔軟性は、特に育児や介護、通勤の負担を減らしたい従業員にとって魅力的です。
多くのIT企業では、リモートワークを導入することで優秀な人材を全国から集めることができ、同時に社員のストレスを軽減し、生産性を向上させた事例があります。
柔軟な勤務形態を導入することで、企業は働きやすさを提供し、結果として人手不足の解消や業務の効率化が図れます。
ワークライフバランスを考慮した職場環境の整備
ワークライフバランスを意識した職場環境の整備は、従業員の定着率を高め、人手不足の解消に効果があります。
従業員がプライベートと仕事を両立できるような環境を提供することで、満足度が向上し、長期的な労働力の確保が可能になります。
また、企業のイメージ向上にもつながり、優秀な人材を引き寄せます。
企業Aでは、育児休暇後の復帰支援やフレキシブルな勤務時間を導入し、特に若い世代の女性社員の定着率が向上した事例があります。
ワークライフバランスを考慮した職場環境は、従業員の満足度を向上させ、長期的に人手不足を解消するために重要な要素です。
外国人労働者の活用と多様性の推進
外国人労働者の受け入れを促進することは、人手不足を解消する重要な手段です。
日本国内では労働力不足が深刻化しており、外国人労働者の活用は、企業の成長に貢献する鍵となります。
特に製造業や農業では、外国人実習生や労働者の受け入れが進んでいます。
製造業では、外国人実習生を受け入れることで生産ラインを維持し、労働力を確保している企業が増えています。
外国人労働者の受け入れを進めることは、企業の人手不足を解消する有効な手段であり、グローバル化の一環としても重要です。
言語サポートや生活支援の強化
言語サポートや生活支援を強化することで、外国人労働者がスムーズに働ける環境を提供できます。
言語や文化の違いによる障壁を取り除くために、生活支援や通訳、文化交流を積極的に行うことが重要です。
これにより、外国人労働者が仕事に集中でき、企業側との摩擦が減少します。
企業Cでは、外国人労働者に日本語教室を提供し、生活支援を充実させることで、労働者の定着率が高まり、業務効率も向上しました。
言語サポートや生活支援を強化することで、外国人労働者が活躍できる環境を整え、人手不足を解消できます。
おすすめ人手不足解消法:「外国人材」の活用

「また求人に応募が来ない…」、「現場のスタッフは疲弊しきっている…」、「このままでは、事業の成長どころか維持すら難しい…」。
企業の未来を担う経営者や人事担当者の皆様から、そんな悲痛な声が聞こえてこない日はありません。
まさに、出口の見えないトンネルを歩いているかのような感覚ではないでしょうか。
しかし、その八方塞がりの状況を打ち破り、会社を新たな成長軌道に乗せるための、確かな光が存在します。
数ある人手不足解消法の中で、今最も強くおすすめしたい解決策は「戦略的な外国人材の活用」です。
なぜ今、「外国人材」が最強の切り札なのか?
「外国人材というと、手続きが複雑でコストもかかるのでは?」、「言葉や文化の壁が心配だ…」。
そう思われるのも無理はありません。
しかし、その懸念を乗り越えるだけの大きなリターンが外国人材にあるからこそ、私たちは強くおすすめするのです。
その理由を、客観的なデータと共に解き明かしていきましょう。
日本で働く外国人材は、2023年には過去最高の約205万人に達しました。
多くの先見性ある企業は、既に外国人材を「コスト」ではなく「投資」と捉え、力強い成長の原動力としているのです。
「でも、やっぱりコストが…」という声が聞こえてきそうですね。そこで注目したいのが、「コストパフォーマンス」という視点です。
「外国人材はコスパが良い」とは、決して「安い労働力」という意味ではありません。
法律上、日本人と外国人材に同等の賃金を支払うのは当然の義務です。
私たちが指す外国人材の「コスパの良さ」の正体は、以下の点にあります。
| 外国人材の「コスパが良い」本当の意味 | 解説 |
| 圧倒的な「意欲」と「定着率」 | 「日本で技術を学びたい」「家族のために稼ぎたい」という強い目的意識を持つ外国人材は、驚くほど学習意欲が高く、一度信頼関係を築けば、簡単に離職しない大きな戦力となります。 |
| 「助成金」という追い風 | 国も外国人材の活用を後押ししており、教育や環境整備に対して様々な助成金を用意しています。これらを活用すれば、受け入れの初期投資を大幅に抑えることが可能です。 |
| 組織を活性化させる「新しい風」 | 異文化に触れることで、日本人社員の視野が広がり、コミュニケーションは活性化します。多様な価値観は、マンネリ化した組織に新しいアイデアやイノベーションの種を蒔いてくれるのです。 |
人手不足という大きな壁に立ち向かうための道筋が、少し見えてきたのではないでしょうか。
戦略的な外国人材の活用は、目先の欠員を埋める「応急処置」ではありません。
それは、会社の生産性を高め、組織を活性化させ、未来の成長基盤を築くための「戦略的投資」なのです。
勇気を持って一歩を踏み出した企業だけが、人手不足を乗り越えた先にある、新しい成長の景色を見ることができます。
企業の人手不足解消:まとめ
企業の人手不足解消には、効率的な業務の自動化や社員のスキルアップ、そして多様な人材の活用が重要です。
人手不足解消の鍵は「戦略的な外国人材活用」にあります。
これは「安価な労働力」ではなく、高い意欲がもたらす生産性向上や組織活性化など、トータルリターンが大きい「コストパフォーマンスに優れた未来への投資」です。
人手不足という壁を乗り越え、会社の新たな成長物語を始めるために、まずは情報収集からその一歩を踏み出してみませんか。
外国人採用に興味やご不明な点がございましたら、以下ボタンからお気軽にお問い合わせください。