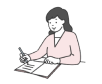外国人実習生の労働条件!違反しないための基礎知識

外国人実習生の労働条件!違反しないための基礎知識
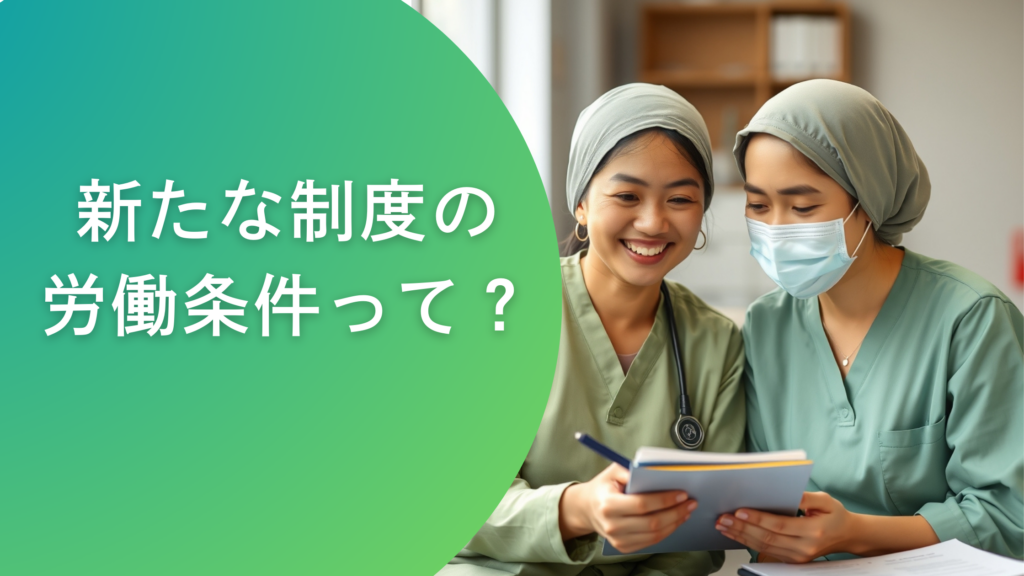
日本で働く外国人技能実習生は、「学びながら働く」という制度のもとで、さまざまな職場で活躍しています。
しかし、実際の現場では、労働時間や賃金、休日などの労働条件について、十分な理解がないまま働いているケースも見られます。
日本の法律では、外国人実習生であっても労働者としての権利があり、労働基準法などのルールが基本的に適用されます。
この記事では、外国人実習生が知っておくべき労働条件の「適用ポイント」について、分かりやすくご紹介します。
この記事でわかること
- 2024年改正「育成就労制度」の導入
- 外国人実習生の労働条件について
- 労働条件のトラブル対策と相談窓口一覧
外国人技能実習制度の概要
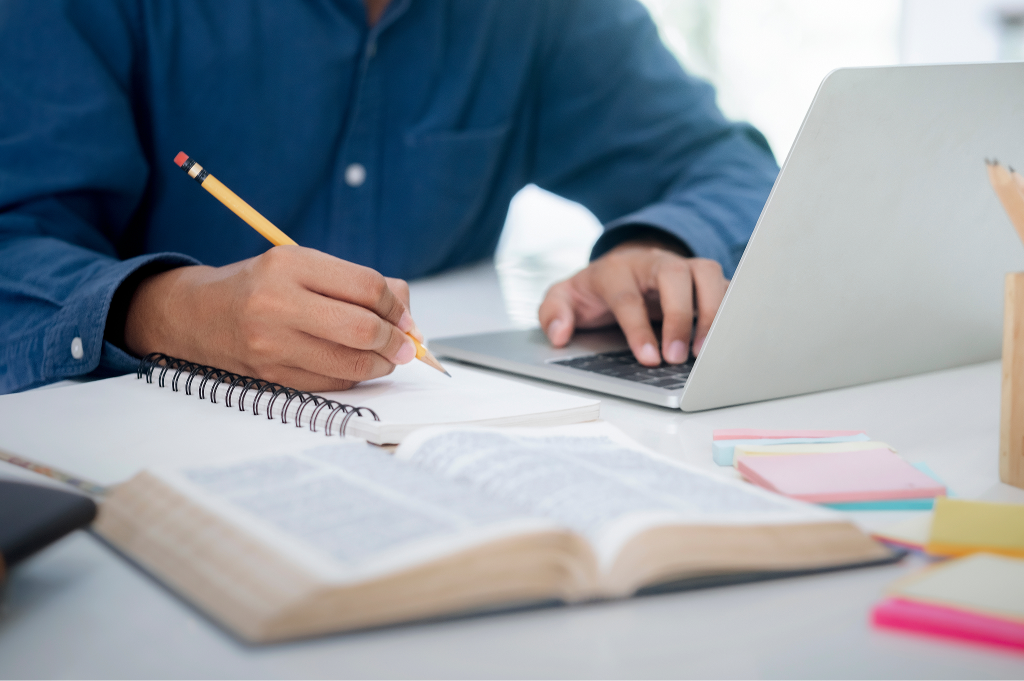
外国人技能実習制度は、日本の技能や技術を開発途上国へ移転し、これらの国々の経済発展を担う人材育成に寄与することを目的としています。
外国人技能実習制度:受け入れ方式の種類と違い
外国人技能実習制度には、「企業単独型」と「団体監理型」の2つの受け入れ方式があり、それぞれ受け入れ主体や実習生の管理方法が異なります。
| 方式 | 概要 | 特徴 | 例 |
| 企業単独型 | 日本の企業が自社の海外現地法人や取引先企業の職員を直接受け入れ、実習を行う方式 | – 企業が直接受け入れ – 自社の技術やノウハウを教える | 製造業企業が自社の海外工場の従業員を招いて技術を習得させる |
| 団体監理型 | 非営利の監理団体(事業協同組合や商工会など)が実習生を受け入れ、傘下の企業で実習を実施 | – 監理団体が実習生の管理・支援を行う – 複数の企業で実習が行われる | 農業協同組合が実習生を受け入れ、地域の農家で実習を実施 |
企業単独型は自社の海外拠点との連携強化を目的とし、団体監理型は中小企業や個人事業主が外国人技能実習生を受け入れる際に活用されています。
それぞれの方式には特性があり、受け入れ企業の状況や目的に応じて選択されています。
技能実習制度改正の動向と影響
2024年6月、技能実習制度の廃止と新たな「育成就労制度」の創設を含む入管法・技能実習法の改正が可決されました。
新制度では、企業単独型技能実習のうち、育成就労制度とは趣旨・目的を異にするものの引き続き実施する意義のあるものは、別の枠組みで受け入れを検討することが示されています。
新たな育成就労制度の導入は、外国人実習生の権利保護と労働環境の改善を目的としており、企業はこれに対応する必要があります。
政府と企業の協力体制の構築
政府は、技能実習制度における課題解決のために、企業や監理団体との意見交換を定期的に実施しています。
| 組織 | 取り組み内容 |
| 厚生労働省 | – 特定の業種における労働環境改善のため、ガイドラインを策定。 – 企業に対して労働環境の改善に向けた指導を強化。 |
| 外国人技能実習機構(OTIT) | – 企業と連携し、実習生の生活支援や労働環境の適正化を進める。 – 実習生の適切な処遇を確保し、労働環境の改善を目指す。 |
政府と企業の協力体制は、技能実習制度の効果的な運用と外国人実習生の保護を強化するために不可欠です。
この連携を強化することで、制度の透明性が向上し、外国人実習生がより良い労働条件で技能を習得できるようになります。
外国人実習生の労働条件
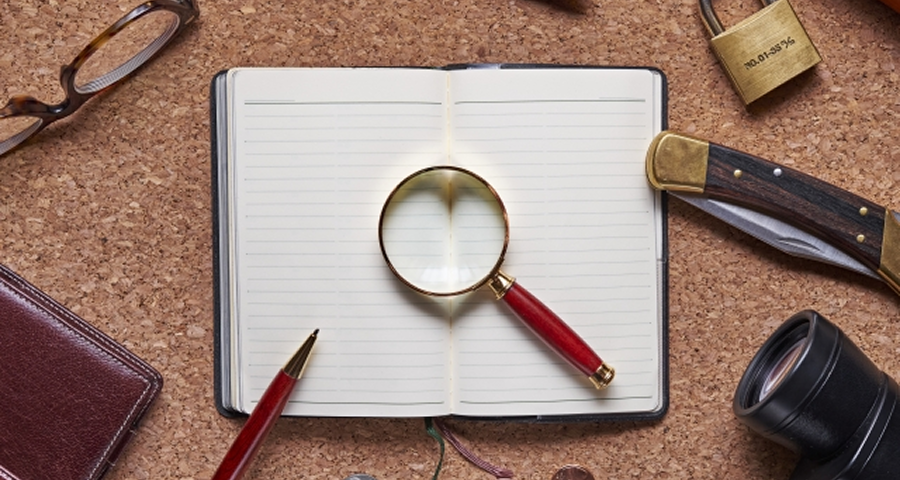
外国人技能実習生の労働条件は、日本人労働者と同等に適用される労働基準法や最低賃金法などの法令に基づき、適切に設定・管理される必要があります。
外国人実習生との雇用契約の締結と明示事項
雇用契約書には、労働基準法第15条に基づき、以下の労働条件を明示する必要があります。
労働基準法第15条では、労働契約締結時に労働条件を明示することが義務付けられています。
外国人技能実習生の雇用契約書に明記すべき主な項目は以下の通りです。
雇用契約書には、労働条件を具体的かつ明確に記載し、労使双方の認識を一致させることが重要です。
【外国人実習生の労働条件】雇用契約書の翻訳と外国人実習生への説明
雇用契約書は、外国人実習生が理解できる言語に翻訳し、内容を十分に説明することが求められます。
外国人技能実習生が労働条件を正確に理解するためには、母国語での契約書と説明が不可欠です。
ベトナムからの外国人技能実習生を受け入れる場合、雇用契約書をベトナム語に翻訳し、通訳を介して内容を説明することで、外国人実習生の理解を促進します。
雇用契約書の翻訳と適切な説明により、外国人技能実習生の労働条件に対する理解を深め、トラブルの未然防止につながります。
【外国人実習生の労働条件】賃金支払いと最低賃金の適用
2024年からの外国人技能実習制度の改正により、賃金の支払いや最低賃金に関するルールが強化されました。
外国人実習生として日本で働く際に大切な労働条件のポイントをしっかりと理解しておきましょう。
【外国人実習生の労働条件】超過労働の割増賃金
時間外労働や休日労働には、法定の割増賃金を支払う必要があります。
労働基準法第37条により、時間外労働や休日労働には割増賃金の支払いが義務付けられています。
通常の労働時間を超える労働には25%以上、深夜労働(午後10時~午前5時)には25%以上、休日労働には35%以上の割増賃金を支払う必要があります。
適切な割増賃金の支払いにより、外国人技能実習生の労働環境の改善と法令遵守が実現されます。
【外国人実習生の労働条件】労働時間、休憩、休日の取り扱い
外国人実習生として日本で働く場合、労働時間や休憩時間、休日に関しても守られるべき法律があります
2024年の外国人技能実習制度の改正によって、外国人実習生の労働環境はさらに改善され、これらの権利が強化されました。
【外国人実習生の労働条件】休憩時間の確保と休日の設定
外国人実習生の労働時間が6時間を超える場合、少なくとも45分の休憩を与え、週1回以上の休日を設定する必要があります。
労働基準法第34条および第35条により、休憩時間と休日の付与が義務付けられています。
【外国人実習生の労働条件】社会保険への加入義務
外国人実習生は、健康保険、厚生年金保険、労災保険、雇用保険などの社会保険に加入する義務があります。
社会保険の加入は、日本国内の労働者全体に適用されるものであり、外国人実習生も同様です。
労働基準法や社会保険法に基づき、適用条件を満たす場合には、必ず加入する必要があります。
社会保険の適用は外国人実習生の生活を支える重要な要素であり、企業がこれを適切に運用することで、外国人実習生の安心感と信頼感を得ることができます。
外国人実習生本人と企業の負担割合
社会保険料は、外国人実習生本人と企業がそれぞれ負担する形で納付します。
日本の社会保険制度では、保険料を労使折半で負担することが義務付けられています。
これにより、双方が適正な負担を分担しながら制度を維持します。
社会保険料の負担割合を明確にし、適正に納付することで、外国人実習生と企業の双方が制度の恩恵を受けられます。
また、これにより、外国人実習生の日本での生活基盤が安定し、実習の成果も向上します。
外国人実習生のハラスメント防止と相談窓口
外国人実習生が安心して働けるよう、ハラスメント防止がしっかりと行われ、万が一ハラスメントを受けた場合でも、相談できる窓口が設けられています。
自分の権利を守るためにも、こうしたルールや相談の仕組みについて理解しておくことが大切です。
外国人実習生へのハラスメント防止策
職場でのハラスメントを防止するためには、企業が明確な方針を策定し、従業員への教育を徹底することが必要です。
厚生労働省は、職場のハラスメント防止対策として、事業主に対し方針の明確化や研修の実施を求めています。
ある企業では、ハラスメント防止のための研修を定期的に実施し、相談窓口を設置することで、職場環境の改善に成功しました。
ハラスメント防止策の徹底は、外国人実習生を含む全従業員の安心・安全な労働環境の構築に不可欠です。
外国人実習生向け相談窓口の活用
外国人実習生は、職場での問題や悩みを相談できる窓口を積極的に活用するべきです。
外国人技能実習機構(OTIT)は、外国人実習生向けに母国語で相談できる窓口を設置し、サポートを提供しています。
外国人実習生が労働条件や人間関係の悩みをOTITの相談窓口に相談し、適切なアドバイスを受けて問題を解決した事例があります。
相談窓口を活用することで、外国人実習生は問題解決の糸口を見つけ、安心して実習に取り組むことができます。
妊娠・出産に関する権利と対応
外国人実習生として働く際、妊娠や出産に関しても、日本の労働基準法や雇用保険法に基づく権利が保障されています。
外国人実習生として日本で働く場合でも、妊娠や出産に関連する法律を理解しておきましょう。
妊娠した場合の対応と休業制度
外国人実習生が妊娠した場合、産前産後休業などの法的権利を行使できます。
労働基準法第65条では、産前6週間、産後8週間の休業を取得する権利が定められています。
| 項目 | 内容 |
| 産前休業 | 産前6週間の休業を取得する権利が定められている |
| 産後休業 | 産後8週間の休業を取得する権利が定められている |
| 取得の権利 | 産前6週間、産後8週間は、従業員が休業を取得することが法律で保障されている |
| 条件 | 従業員が産前産後休業を取得するためには、医師の証明が必要となる場合がある |
ある外国人実習生が妊娠し、産前産後休業を取得した後、職場復帰し、引き続き実習を継続したケースがあります。
妊娠した外国人実習生は、法的権利を理解し、適切な手続きを行うことで、安心して出産・育児に臨むことができます。
外国人実習の職場復帰と支援策
産後の職場復帰には、企業の支援策や柔軟な勤務体制が重要です。
育児・介護休業法では、育児休業や短時間勤務制度の利用が可能とされています。
ある企業では、産後に復帰した外国人実習生に対して短時間勤務制度を導入し、育児と仕事の両立を支援しました。
この外国人実習生は、職場でのサポートを受けながら実習を継続し、技能を習得しています。
産後の職場復帰には、外国人実習生が安心して働けるような労働条件を企業が整えることが必要です。
これにより、外国人実習生の生活の安定と実習の質の向上が期待できます。
外国人技能実習制度における実習実施者の責務

外国人技能実習制度において、実習実施者(受入企業)は、外国人実習生の適切な指導と保護を行う責任があります。
具体的には、技能実習計画の策定・認定、責任者・指導員の選任、労働条件の管理・改善などが求められます。
技能実習計画の作成要件
技能実習計画は、外国人実習生が修得すべき技能や知識、実習内容、期間などを具体的に記載し、法令に基づいて作成する必要があります。
技能実習法では、外国人実習生が計画的に技能を修得できるよう、詳細な実習計画の作成が義務付けられています。
例えば、建設業での技能実習計画では、具体的な作業内容(型枠施工、鉄筋組立てなど)、各作業の実施期間、指導者の氏名と資格、評価方法(技能検定の実施など)を詳細に記載します。
適切な技能実習計画の作成は、外国人実習生の技能習得と企業の責務遂行に不可欠です。
計画は具体的かつ実現可能な内容とし、法令を遵守することが求められます。
外国人実習生を受け入れる認定プロセスと必要書類
技能実習計画は、所管の外国人技能実習機構(OTIT)に申請し、認定を受ける必要があります。
申請には、所定の書類を提出し、審査を経て認定が行われます。
技能実習法に基づき、実習計画の適正性を確保するため、OTITによる認定が義務付けられています。
認定申請時には、以下の書類が必要です。
これらの書類を揃え、OTITに提出し、審査を受けます。
技能実習計画の認定は、実習の適正な実施と外国人実習生の保護に直結します。
必要書類を正確に準備し、適切な手続きを行うことが重要です。
技能実習責任者・指導員の選任と役割
技能実習責任者と指導員は、外国人実習生の指導・監督を行うため、一定の要件と資格を満たす必要があります。
技能実習法では、実習の質を確保するため、責任者と指導員に対し、実務経験や資格の要件を定めています。
また、責任者は、実習全体の管理・監督を行い、外国人実習生の生活指導も担当します。
適切な責任者と指導員の選任は、実習の成功と外国人実習生の成長に直結します。
要件を満たす人材を配置し、外国人実習生への効果的な指導体制を整えることが重要です。
外国人実習生の適正な労働条件の管理
外国人実習生の労働条件は、定期的に見直し、適正な状態を維持する必要があります。
労働基準法や最低賃金法などの法令は、経済状況や社会的要請に応じて改正されることがあります。
適正な労働条件の管理は外国人実習生との信頼関係を強化し、長期的な実習の成功につながります。
トラブル防止のための事前対策
トラブル防止には、事前にリスクを予測し、適切な対策を講じることが重要です。
外国人実習生のトラブルの多くは、労働条件や職場環境に関する不十分な情報提供、あるいは誤解から生じます。
技能実習法では、外国人実習生の保護を強化するため、トラブル発生の防止策を実施するよう企業に求めています。
事前の対策を徹底することで、労働条件のトラブルを未然に防ぎ、外国人実習生と企業双方が安心して実習に取り組める環境を作ることができます。
外国人実習生の労働条件に関する主な違反事例

外国人実習生の皆さんが職場で直面する可能性のある労働条件に関する違反を理解することは、非常に重要です。
自分の権利を守るために、どのような労働条件の問題が発生するのかを知っておくことで、適切な対応ができるようになります。
【外国人実習生の労働条件】賃金未払いの具体例
外国人実習生への賃金未払いは、労働基準法違反となり、企業に対して厳しい罰則が科される可能性があります。
労働基準法第24条では、賃金は毎月1回以上、一定の期日を定めて支払わなければならないと規定されています。
この労働条件に違反する行為は、法的な制裁の対象となります。
ある企業で、外国人実習生に対して数ヶ月間にわたり賃金の一部が未払いとなっていた事例があります。
| 事例 | 詳細 |
| 問題発生 | 企業が外国人実習生に対し数ヶ月間、賃金の一部を未払い。 |
| 是正勧告 | 労働基準監督署から未払い賃金の支払いと再発防止策の実施を求められる。 |
| 未払い賃金の支払い | 速やかに全額の未払い賃金を支払う。遅延があった場合は、利息なども加算される可能性がある。 |
賃金未払いは重大な法令違反であり、企業の信用失墜や法的制裁を招く可能性があります。
適切な労働条件、賃金支払いを徹底することが求められます。
外国人実習生におすすめ:相談窓口と支援機関の活用方法

公的機関の相談窓口を把握し、適切に活用することで、問題解決への道筋が開けます。
各種公的機関は、労働条件や人権に関する相談を受け付けており、専門的なアドバイスや支援を提供しています。
| 機関名 | 相談内容 | 連絡先 |
| 労働基準監督署 | 賃金未払い、労働時間の問題、労働条件 | 各都道府県労働局に所属する労基署 |
| 外国人技能実習機構(OTIT) | 外国人実習生の労働条件、生活支援 | OTIT公式サイト |
例えば、外国人実習生が労働条件に関する相談を労働基準監督署に行った結果、未払い賃金の支払いと労働時間の是正が実現したケースがあります。
公的機関の相談窓口を活用することで、外国人実習生は安心して問題を解決でき、企業側も適切な指導を受けられます。
支援団体の役割と利用方法
支援団体は、外国人実習生の生活や労働環境の改善を目的とした重要なサポートを提供します。
これらの団体を適切に活用することが労働条件などのトラブル解決につながります。
支援団体の活用は、外国人実習生の権利保護と問題解決の大きな助けとなります。
企業と外国人実習生が連携し、これらの団体を活用することで、より健全な労働条件や実習環境が実現します。
外国人実習生の労働条件:まとめ
2024年から外国人技能実習制度は「育成就労制度」へ移行し、外国人実習生の権利保護と労働環境の改善が進められました。
新制度は外国人実習生が安心して働ける環境を作ることを目的としており、企業は言語の壁や労働条件の課題を解決する責任があります。
政府と企業が連携し、外国人実習生が安全で快適な環境で働けるように取り組み、労働力不足の解消にもつながります。
外国人実習生は新制度でより良い労働条件で働きながらスキルを習得でき、より良い未来を築くことが期待されています。